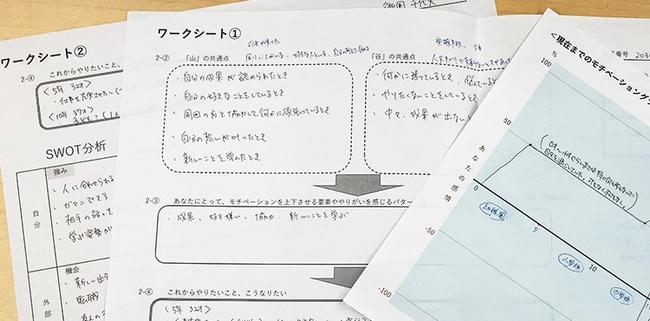厚生労働省は現在、地域の包括的な支援やサービス提供の体制として「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。その実現に向けて、ウエルシアが運営に関わっている地域包括支援センター(※)が「ウエルシアハウス」です。今回は人事本部 薬剤師採用部の須賀が実際にウエルシアハウスへ訪れて、どんなことを行っているのかなどの話を聞いてきました。
※介護予防ケアから金銭トラブルの相談まで、いわゆる行政サービスを無償で提供する場所。
信用してもらうところから始まった

「最初の頃は、地域の人が信用してくれなかったんだよ。看板にウエルシアの文字があるからさ」
センター長の福田さんは、オープン当時のことをそう教えてくれました。主に行政が運営している地域包括支援センターですが、行政の委託で民間企業が運営するのは全国的に珍しく、関東で初めて誕生したのは2017年。それが、ウエルシアハウスでした。
須賀「たしかに、地域のドラッグストアがやってくれるなんて、普通思わないですよね」
福田「相談しに行ったら何か売りつけられると思ってる方も多かったよ。“何でも相談に乗ってくれるのに、無料なのはおかしい”って」
須賀「無料って言われたら逆に身構えちゃうから、ホンネの相談はしづらいかも」
福田「だから、最初のうちは、私たちから商品の紹介を一切しなかった。もうそれこそ意地だったよ(笑)
定期的に、相談会やセミナーイベント、おしゃべり会をして、少しずつ地域の一員になっていくのを感じてた。そこから相談にくる方も増えたね」
薬剤師の必要性を痛感

相談件数が増えてくると、福田さんは相談者に共通する「ある問題」に気付いたそうです。
須賀「どんな問題ですか?」
福田「高齢者の一人世帯が増えて、医療が家まで届かなくなった。せっかく退院して家に帰っても、見てくれる人がいないから、しばらくするとまた入院してしまう」
須賀「家で様子を見てくれる家族がいない、と」
福田「生活と医療をセットで支えていく必要性を感じたんだ。たとえば、ゴミ屋敷に住み、在宅医療を受けている女性。診断と処方をする医師と、薬の管理をする薬剤師。家の中にたくさんの困った問題があるのに、うまく介入できてない。ちょっとくらいゴミの片づけしてあげればいいのにって思う」
須賀「医療者が医療しかみてないってことですね」
福田「そうそう。たとえば、奥さんが急遽入院することになって、いきなり一人暮らしを始めることになった高齢の男性は、自分の下着もコップの位置さえ分からなくて、薬どころじゃないんだよね」
須賀「たしかに…」
福田「健康を守るためには、生活も守っていかなきゃいけない。全科対応ができて、医療と生活の両面からケアの出来る薬剤師が一番サポートできると思ってるんだ」
須賀「薬剤師が一番向いてるってことですか?」
福田「そう!薬剤師は、医療と生活の両方を知っている唯一の医療職として、可能性のかたまりだよ。全科対応できて、薬から生活を見れて、生活用品を扱える医療者なんて、薬剤師しかいないよ。地域の生活の問題も、全科的な医療も、ウエルシアの薬剤師なら介入できる。病院や薬局じゃできないし、医師や看護師でもできない領域なんだ」
薬剤師の可能性について、語気を強めて熱弁する福田さん。トータルケアという言葉の意味を、あらためて考えさせられました。
大事なのは人との食事

取材当日は、「おひとりさまの会」をしていました。死別や配偶者の病気で"おひとりさま"の方が、集まって食事とおしゃべりをする会です。
農家の方が、ヨモギとウドとジャガイモを持ち寄り、調理師の方が、高齢者に合わせて調理してくれました。
終始、笑顔とおしゃべりが絶えない会で、みんなが地域を意識して支えようとしているのが印象的でした。この会を開いている地域の方にも話を聞いてみました。
須賀「この会は長いんですか?」
地域の方「もう何ヶ月もやってるよ。週に1回のペースで、なんだかんだ続けられてるね。ひとりになって誰とも会わないと、元気なくなっちゃうじゃない?どうにかみんなに来てもらえるように、美味しいごはんでつってるの(笑)」
須賀「農家の方や、調理師の方、いろんな方が協力してくれてるんですね」
地域の方「自分たちが住んでるこの町が好きだからね、ほっとけない人の集まりなんだよ。そういう場所をウエルシアが作ってくれて本当に感謝してる。いままでなかったんだから」
この会に、3ヵ月参加を続けているある方は、杖もつかなくなり、顔の血色も良くなったそうです。「人と会って、ご飯を食べる、笑顔でおしゃべりをする。それが健康の秘訣」とみんな口を揃えて言っていました。


お返しの好循環
福田「出来てから5年経って、いまではウエルシアに寄ってくれる方も多いんだよ。無料で申し訳ないから、帰りに何か買って帰るよって」
須賀「善意で支え合う地域の輪に、ウエルシアもちゃんと入れたんですね」
福田「買う物ないんだけどいつも助けてもらってるから、って何買おうか一生懸命考えてくださるんだ。その気持ちがとっても嬉しいよ」
最後に、これからのウエルシアハウスについて、福田さんに聞いてました。
福田「ウエルシアを利用してくださる方々と地域が、私たちを育てて、ここまで会社を大きくしてくれた。その還元をもっと広めていきたい。お返しをしなきゃいけないのはウエルシアのほうなんだ」
須賀「そうですね」
福田「これからも、人と人が向き合って頼れる場所、地域の何でも屋をしていきたい。地域の支え合いの輪をもっともっと大きくした、素晴らしい包括ケアシステムを構築していきたい。それができるパワーをウエルシアは地域から貰っていると思うよ。社会に良いことをする。これが僕の仕事で、誇りでもある。儲かる場所、売上が高い場所で働くことは誇りにならないからね」
センター長の福田さんだけでなく地域の方も含め、みんなが当事者意識を持って支え合う形こそ地域包括ケアなんだ、と改めて再認識しました。
身近な生活の問題がこんなにもたくさんあるのに、医療者による介入がうまく出来ていない現実もあります。また、行政運営では解決まで届かない問題もあります。
薬局もあり、生活用品も扱うウエルシアが運営する地域包括支援センターの可能性。医療と生活の隙間を埋めることで、地域包括ケアシステムの構築は前に進みます。
それができるかどうかは、薬剤師に掛かってるってワクワクしませんか?
機会があれば、ぜひウエルシアハウスに見学に来てください。